コミュニケーションを図るのと取るは何が違う?

「図る」とは?その意味と使用例
「図る(はかる)」は、ゴールに近づくための準備・調整・設計に重心がある言葉です。
たとえば「理解を図る」「合意形成を図る」は、関係者の利害や感情を読み取り、段取りを整え、場を整備することで結果の出やすい状態をつくることを意味します。
会議体の設計、情報の事前共有、根回し、稼働の見積もりなど、プロセス全体を見渡す行為が中核です。
“いま何をすれば相手が動きやすくなるか”を先回りして用意するニュアンスが「図る」の核心で、単発の連絡や依頼だけでは到達しない質的な変化を狙います。
「取る」とは?その意味と使用例
「取る」は、相手と接点を生み出す実行そのものを指します。
メールを送る、電話する、打ち合わせの機会を押さえる、Slack でメンションする等が典型です。
「連絡を取る」「時間を取る」「面談の機会を取る」は、準備済みの仮説を現場で検証するためのアクションであり、成果の起点となります。
注意したいのは、色々“取って”いても設計が弱いと空回りしやすい点です。
「図る」で地ならしし、「取る」で前進させる――この二段構えが実務では最も再現性の高い進め方になります。
図ると取るの混同が生まれる理由
両者は時間軸で連続し、どちらも“コミュニケーション”と結び付くため、発話上は置換が起こりやすいのです。
社内では「関係各所と連携を取っておきます」のような表現も耳にしますが、実際は「連携体制を図っておきます」がより本質的です。
体制・関係性・合意といった“目に見えにくい資産”を整えるのが図る、接触・取得・実施という“見える行動”が取る。
このフレームを共有すると、依頼の精度が上がり、手戻りが減ります。
実際の例で見る違い
例1:トラブル後の「信頼回復を図る」は、原因分析の透明化、謝罪の段取り、影響範囲の説明方法の整備など、回復の条件づくりが主眼です。
例2:「キーパーソンと面談の時間を取る」は、実際のアポイントを押さえる行為。
例3:「部署横断の連携を図る」では、会議体の設計や責任線の明確化が中心。
例4:「見積り内容の認識を取る」は口語では通じても、書面では「認識を合わせる/確認する」が適切です。
“構造を整えるのか、接点をつくるのか”で言葉を選ぶと意思疎通が格段に滑らかになります。
意外なシーンでの誤用
「合意を取る」はビジネス口語として広まっていますが、正式文書では「合意を得る」が無難です。
また「関係者と連絡を図る」は不自然で、ここは「連絡を取る」が適切。
結果の質向上や体制整備など“状態の改善”は図る、問い合わせや確認など“行為の実施”は取ると覚えると迷いにくくなります。
言い換えに詰まったら、動詞を「整える/深める/設計する」と「連絡する/確認する/依頼する」に分解して考えるのがコツです。
コミュニケーションを円滑にするためのポイント
意識すべき非言語コミュニケーション
非言語は内容以上に印象を左右します。視線・姿勢・うなずき・間の取り方、オンラインではカメラ位置や照明も影響大。
話す速度を相手に合わせ、要所で短い要約を添えるだけで“わかってくれている”感覚が生まれ、受け取り手の負荷が下がるものです。
加えて、反応が薄いときは画面外の事情を想定し、チャットで要点を重ねて補完すると誤解を防げます。
「どう見えているか」を設計するのは、まさにコミュニケーションを“図る”段階の重要タスクです。
相手のニーズを汲み取る重要性
相手の関心・懸念・制約を想像し、検証し、反映するほど話は通ります。
おすすめは、①オープンクエスチョン→②要約返し→③提案→④合意の小さなループ。
相手の言葉を要約し直すだけで誤解が可視化され、ズレを早期に修正できます。
判断者・利用者・実装者などステークホルダー別の期待を整理し、誰に何のベネフィットがあるのかを一文で示すと、合意形成を図る際の摩擦が大きく減ります。
誤解を避けるための確認方法
会話の最後に 30 秒の要約を入れる、日時・責任者・成果物を並べたミニ ToDo を残す、記録の格納先を固定する――この三点だけで齟齬は激減します。
「何をいつまでに誰がやるか」を文章化し、翌日も参照できる形で残すことが重要です。
言質は会話ではなく記録に宿るため、議事録・タスク管理・チケット化のいずれかへ必ず落とし込みましょう。
認識ズレが起きたときは、非難より「前提の違い」を丁寧に棚卸しするのが早道です。
「図る」と「取る」を使い分けるためのヒント
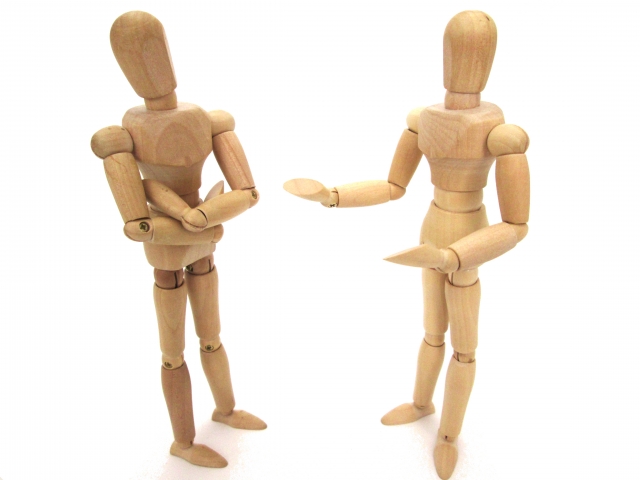
シチュエーション別の使い方
新規プロジェクトの立ち上げなら「関係者の期待値調整と意思統一を図り、初回ミーティングの予定を取る」。
顧客対応では「不安要因の洗い出しと説明方針を図り、フォロー電話の時間を取る」。
採用なら「評価基準の整備を図り、候補者との面談枠を取る」。
目的(状態の改善)と手段(接触の実施)を二層で考えると、言葉の選択が自動化されます。
この型をチームで共有すると、依頼・報告・レビューの質が均一化します。
ビジネスにおける正しい選択
メール・議事録・手順書では、段階を分けて記述するのが効果的です。
例:「①関係各所との合意形成を図る(期限:金曜)/②決裁者との打合せを取る(来週前半)」のように時系列で並べると、読者は迷いません。
「図る=意思と設計」「取る=行動と実行」と明示する文章は、読み手の行動を引き出しやすく、指示の解像度を上げます。
迷うときは、代替動詞(整える・深める/連絡する・確認する)への置換でチェックしましょう。
コミュニケーションを育むために必要な考え方

相手との信頼関係の築き方
信頼は“期待通り”の反復から生まれます。
約束時間の厳守、議事録の即時共有、未確定情報を曖昧にしない――こうした地味な行動が積み上がってようやく信用になります。
ミスが起きたときは、影響範囲の提示→暫定対応→恒久対策という順で開示し、回復プロセスを可視化すると、ダメージを最小化できます。
「相手の時間を奪わない」「相手の立場で考える」を設計段階から織り込むことが、長期的な関係を育てます。
コミュニケーションスタイルの理解
人は情報の受け取り方に癖があります。結論先出しが安心な人もいれば、背景説明がないと動けない人もいます。
相手の反応(質問の質・沈黙の長さ・メモの頻度)からスタイルを仮説立て、文章量・語彙・媒体を微調整することで、同じ内容でも伝達効率が大きく変わります。
初回は短文+図解、二回目以降は詳細資料、などの“段階設計”も有効です。
スタイル適応は「図る」の重要要素であり、チームの摩擦を減らします。
まとめ:コミュニケーションの質を向上させるために
「図る」は設計と準備、「取る」は接点と実行。
この二語を意識的に切り分け、文章と行動を段階化するだけで、意思疎通は驚くほど滑らかになります。
まずは、毎日の依頼文に「何を図り、何を取るのか」を一行で書き添えることから始めましょう。
言葉の精度は、チームの速度。今日の一通のメッセージから、品質の高いコミュニケーションを育てていきましょう。

